トップ > 県教育委員会トップページ > 教育長の部屋
ページID:97542更新日:2025年8月21日
ここから本文です。
教育長の部屋
荻野教育長
第38回関東地区学校図書館研究大会甲府大会 祝辞(令和7年8月7日)
第38回関東地区 学校図書館研究大会 甲府大会が盛大に開催されますことを、心よりお慶び申し上げます。
山梨県教育委員会では、生成AIをはじめとする情報通信技術の急速な進化が、社会のあり方そのものを劇的に変えつつある現代において、児童生徒が「正解のない課題」に向き合い、自ら考え、判断し、行動できる力を育んでいくことが求められていると考えます。
そのため本県では、全国に先駆けて進めている少人数の教育の環境を活かし、児童生徒が自ら課題を設定して取材を行い、自分なりの解決策を模索するいわゆる「探究的な学び」を、小・中・高を通じて一貫的に進めていこうと考えています。
もとより学校図書館は、児童生徒の興味・関心等に応じて、自発的・主体的に読書や学習が行われる場でありますが、こうした探究的な学びを進めるため、情報の収集や選択を通じて、情報活用能力を育成する場としての「レファレンス機能」も充実・拡大させていきたいと思っております。
本県では、令和6年3月に「第4次 山梨県子ども読書活動推進実施計画」を策定し、すべての子どもたちに豊かな読書体験を届けるための環境整備を進めているところです。
平成26年にスタートした「やまなし読書活動促進事業」におきましても、図書館と書店が連携して、官民一体で子どもの読書への意欲を喚起し、豊かな読書体験を届けるために数々の取り組みを行ってまいりました。
私は読書を趣味としていますが、教育長就任のあいさつの中で、先生方に向けて、「自分の専門分野だけでなく、様々なジャンルの本をたくさん読んでほしい」と申し上げました。
それは、読書を通じて見識を広めることが、子どもたちに語りかける言葉に深みと説得力を与えると確信しているからです。
また、子どもたちにとっても、読書は社会や新しい世界、そして自分とは全く異なる生き方と出会う貴重な体験です。
その読書体験は、わくわくする時間であると同時に、子どもたちの既存の考え方(スキーマ)を揺さぶり、一面的な情報に基づく思い込みに気づくきっかけとなり、より深い理解や多角的なものの見方へと導く機会になるものと考えています。
さらに、先日公表された全国学力・学習状況調査の結果分析でも、「読書は好きか」という設問に対し「好き」と回答した児童生徒は、小学生・中学生とも国語、算数・数学、理科の全ての教科で成績が良かったと報告されています。
このことに関連して文部科学省は、「読書は各教科の言語活動を支える基盤であり、本を身近に感じる取り組みが必要である」と分析しています。
各都県の学校図書館教育を最前線でけん引しておられる皆様が一堂に会し、各テーマについて学び、協議する熱い時間を共有されますことは、「子どもたちの主体的な学びと読書活動を支える」という、今大会のテーマの実現に資する、意義深いものであると確信しております。
本大会を通して、これからの図書館および図書館教育のあり方について、実りある成果が得られ、全国の児童生徒一人ひとりの豊かな心の涵養とウェルビーイングにつながりますことを心より願っております。
郷土の俳人 飯田龍太は、山梨県の暑い夏を「急流に のめりてそそぐ 炎暑かな」と詠んでいます。
立秋を過ぎたとはいえ、まだまだ厳しい暑さが続いております。大会後の週末には、是非富士五湖や各地の渓谷などに足をお運びいただき、山梨を象徴する美しい山々から流れ出る清らかな水と、清涼感あふれる空気に触れながら、日頃のお疲れを癒やしていただければ幸いです。
また、この時期には、桃や、すもも、ぶどうなど、フルーツ王国山梨ならではの旬の果実をお楽しみいただけるほか、ワインやほうとうなどの特産物もお土産としてご好評いただいております。
本県でのご滞在が、皆様にとって心に残るひとときとなることを願っております。
第1回山梨県地域クラブ活動推進連絡会(令和7年7月22日)
日頃より部活動をはじめとする本県の学校教育活動にご理解とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。
さて、皆様もご承知のとおり、国は「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議」を開催し、最終とりまとめを発表いたしました。
今回の部活動改革の主な目的は、急速に進む少子化の中にあっても、生徒が将来にわたって継続的にスポーツや文化芸術活動に親しむ機会を確保・充実させることにあります。
さらに、学校だけでなく地域全体で関係者が連携して部活動を支え、生徒に豊かで幅広い活動機会を保障することが改革の理念とされているところです。
最終とりまとめでは、この理念をより的確に表すため、「地域移行」という名称を「地域展開」に変更し、次期改革期間である「改革実行期間」に向けての方向性が示されました。
本県でも、今後はこの「地域展開」という言葉を積極的に使っていきたいと考えております。
改革の実現に向けた手法を検討する際には、質の高い指導の実現を目指すことはもちろんですが、学校における働き方改革の観点も考慮する必要があります。
私自身も生徒や学生として、また教職に就いてからは部活動の顧問として、40年以上にわたり運動部活動に係わってまいりました。
部活動を通じて得た経験や人とのつながりは、今も私自身を支える大きな財産となっています。
今まさに、日本の教育が世界に誇るこの「部活動」という文化を、持続可能な形で後世に残すことが出来るかどうかの分岐点に差し掛かっているのではないかと感じております。
この歴史的とも言える改革を進めるためには、本日御参会いただいている皆様と適切に役割分担を行い、県や地方公共団体とともに幅広い関係者が連携・協働しながら一体となって取り組んでいく必要があると考えます。
本日は、各市町村の進捗状況を踏まえて、本県における地域クラブ活動推進のための方策などについて提示させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
甲府工業高校専攻科創造工学科への寄附受納式(令和7年7月7日)
ヴィジョナリーパワー株式会社(代表 戸田達昭)から甲府工業高校専攻科創造工学科への寄附受納式が行われました。
これは、同社の理念である創業報県のもと、その恩恵を県に還元するため、「UVプリンタ」などの設備購入や「ソーラーカー大会」への参加などのアウトリーチ活動に対し、ご寄附をいただいたものです。
また、受納式の後は制作中のソーラーカーを見学し、戸田代表から生徒に激励が送られました。


山梨大学「やまなしジュニアドクター育成自然塾」入塾式(令和7年6月29日)
山梨大学が実施するやまなしジュニアドクター育成自然塾(※)の入塾式に出席し、挨拶を述べました。
科学技術・イノベーションの将来を担う次世代科学者を育成するため、小中学生を対象として山梨大学が実施する教育プログラムです。詳しくは下記ホームページから。
やまなしジュニアドクター育成自然塾 – 南アルプス・ユネスコパークでの活動が育む未来人材


現代は変化のスピードが非常に速く、将来を予測するのが難しい時代であると言われます。今日の常識が明日の非常識になりかねない、そんな時代を生き抜いていく子どもたちには、様々な問題を自ら主体的に考え、常に学び続けようとする姿勢が求められていると考えます。
発明王エジソンは「白熱電球のフィラメントとして最適な素材は何か」という課題を探究し、1万回以上の実験を繰り返した結果「京都の竹が最適である」という結論を得たと言われています。彼はこの経験について後に、「私は失敗したことはない。ただ、1万通りのうまくいかない方法を見つけただけだ」と語ったそうです。
本日入塾された小中学生の皆さんにも、皆さんが生来持っている「好奇心」を大切にして課題を見つけ、エジソンのように挑戦と失敗を「経験」に置き換え、常に主体性を持って「探究」を続けていってほしいと願っています。
山梨県教育委員会では、「主体的に学び 他者と協働し 豊かな未来を拓く やまなしの人づくり」を基本理念とした、山梨県教育振興基本計画を令和6年度に策定し、一人ひとりの関心・意欲や特性に基づいた「子どもの力を伸ばす学び」の実現を目指し、各種施策に取り組んでいるところです。
私たちの郷土は、世界文化遺産富士山をはじめ、八ヶ岳、南アルプスエコパーク、美しい湖水や星空など、科学的感性を刺激する豊かな自然に恵まれています。
この素晴らしい環境の中で、皆さんには、山梨大学の先生方の専門的な指導の下、自由な発想で自分なりの疑問や課題を見つけ、解決に向けて試行錯誤しながら、科学的なものの見方や考え方を身につけてほしいと思っています。
お集まりの保護者の皆様には、今回の自然塾の活動がお子様の学習意欲を高め、新たな可能性の発見につながるよう、そして子どもたちが、これからのよりよい山梨、よりよい日本、そしてよりよい世界の創り手となってもらえるよう、その成長を温かく見守っていただきたいと思います。
第1回夜間中学・学びの多様化学校設置検討有識者会議(令和7年6月13日)
夜間中学及び学びの多様化学校について意見聴取するため新たに設置された有識者会議に出席し、挨拶を述べました。


本県の不登校の児童生徒数は年々増加し、令和5年度は2,189人で、10年前と比べ約2.6倍となっています。急速に進行する人口減少社会において、学校や社会とのつながりが希薄な子どもたちの増加は、極めて深刻な社会問題となっています。
また、県内には、義務教育課程を修了していない方が7,000人以上いるとされ、さらに、母国で十分な教育を受けられなかった外国人の方々や、中学校を卒業はしていても、もう一度学び直したいと考える方々も、一定程度いらっしゃるものと推測されます。
これまで学ぶ機会に恵まれなかった人が再び学びたいと思った時に、学びにアクセスできる環境を整備し、将来の社会的な自立に向けて支援することは、まさに教育の原点に立ち返る取り組みであると考えます。
夜間中学や学びの多様化学校は、本県が教育振興基本計画で掲げる、「誰もが教育の機会にアクセスできるやまなし」の実現に向けて、重要な役割を果たすものと確信しております。
本日は、学識経験者や教育関係者の皆様に加え、実際に不登校やひきこもり支援に携わっていたり、在留外国人や高齢者を支援されたりと、日頃から要支援者と向き合い、現場の声を的確に捉えていらっしゃる皆様にもお集まりいただきました。
ご参会の皆様の豊かな知見と経験を結集し、山梨県にふさわしい夜間中学や学びの多様化学校の在り方について、ぜひ建設的なご議論を賜りますようお願い申し上げます。
本会議での議論が、県民すべてに開かれた学びの場の創出に向けた礎となることを心より願い、私の挨拶とさせていただきます。
令和7年度山梨県PTA協議会定期総会(令和7年5月31日)
山梨県PTA協議会定期総会に出席し、挨拶を述べました。


令和7年度山梨県高等学校PTA連合会定期総会(令和7年5月23日)
山梨県高等学校PTA連合会定期総会に出席し、挨拶を述べました。
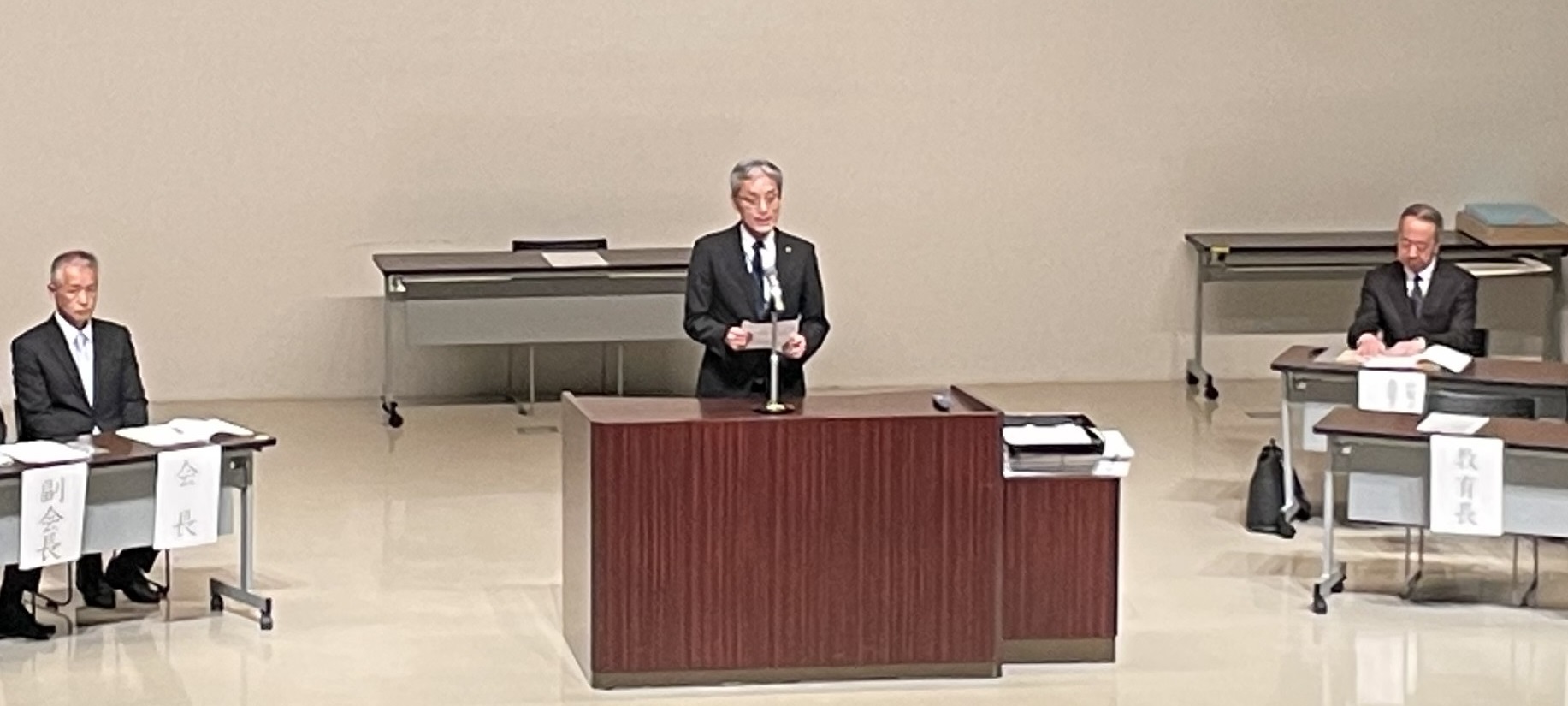
まず、PTA活動を通じて各校の教育活動の充実と子どもたちの健全育成に御尽力いただいていることに、深く感謝申し上げます。
さて、近年の情報技術の急速な発展は、子どもたちの学びの環境を大きく変えました。YouTubeや生成AIを駆使すれば、教師から一斉に教わるより、圧倒的に個人に特化した方法で学べる時代が、既に到来しています。
学びを「既存の情報の獲得」と捉えていては、学校に通うことが絶対の選択肢ではなくなりつつあります。動画やAIだけでは決して実現することのない、学校にしかない学びとは何かを、我々大人が真剣に考える必要があると感じています。今こそ、「学びの本質」に立ち戻るチャンスなのかもしれません。
認知科学の知見は、必要なときに使える「生きた知識」は誰かから与えられるものではなく、例えば母国語のように、他者との交流や実体験を通じた試行錯誤の中で、子どもが自ら発見したり、腹落ちしたり、解釈したりしたものだと教えています。AI時代の学校が注力すべきは、まさにそのような、対話と体験をベースにした学びなのではないでしょうか。
昨年3月に策定した「山梨県教育振興基本計画」では、教員が自らの授業観を「生徒主体」に転換し、子ども一人ひとりの個性や関心・意欲を重視した「誰もが可能性を伸ばせる教育」の推進を目標に掲げています。教員が授業を工夫するための「余白の時間」を作り出すため、働き方改革にも取り組んで参ります。
教育委員会では「地域に開かれた教育課程」の実現に向け、令和8年度までにすべての県立学校をコミュニティ・スクールに移行することにしています。PTAの皆様方には学校運営の一翼を担い、地域から学校や教員を支えていただき、我々の未来を託す子どもたちを、ともに愛し育んで参りたいと考えています。
令和9年度全国高等学校総合体育大会山梨県実行委員会設立総会・第1回総会(令和7年5月22日)
 令和7年5月22日、令和9年度全国高等学校総合体育大会山梨県実行委員会設立総会・第1回総会を開催しました。
令和7年5月22日、令和9年度全国高等学校総合体育大会山梨県実行委員会設立総会・第1回総会を開催しました。
荻野教育長が山梨県実行委員会会長に就任し、2年後となる令和9年度全国高等学校総合体育大会の開催に向けて、より本格的な準備・運営を進めていきます。
第77回 山梨県高等学校総合体育大会春季大会開会式(令和7年5月7日)
山梨県総体開会式に荻野教育長が登壇し、激励を述べました。

爽やかに風薫る5月を迎え、絶好のスポーツシーズンとなりました。
本日から3日間、本県高校スポーツ最大の祭典である、第77回山梨県高等学校総合体育大会春季大会が、県下40校、総勢6,000名を超える選手と、その活躍を見守る多くの高校生の参加を得て、このように盛大に開催されますことを、心からお祝い申し上げます。
この大会は、高校生の皆さんの健全な心身の育成と、生徒相互の信頼と友情を育むことを目的として開催されるものです。
本大会での経験が、出場する選手のみならず、応援する生徒も含めたすべての高校生の成長に資することを、また、本大会をきっかけとして、生徒、教職員、保護者が「チーム学校」としての結束力を高めていただくことを、心より期待しております。
私は、学校教育における運動部活動は、心身の成長と豊かな学校生活の実現に向けて大きな役割を果たすとともに、皆さんがこれから社会に出て行く上で必要となる「生きる力」を養うものであると考えています。
「偶有性」という言葉をご存知でしょうか。「偶有」は「偶然の偶」に「有る」と書きます。「他の状態でもありえたのに、たまたま現在の状況にあること」という意味ですが、私にはこの言葉がスポーツの本質を突いているように思えてなりません。
皆さんは懸命の努力を重ね、勝利を目指して、本日この場に立っています。一方で、皆さんと同じように日々努力している選手がいることもまた事実です。
弱者が強者に勝つ「ジャイアントキリング」という言葉もあるように、実力が必ずしも結果に結びつくとは限らない。勝負はやってみなければ分かりません。
努力をすればするほど、試合で勝つことがたまたまの産物ではないことが分かります。一方で、試合をすればするほど、努力したからといって、いつも勝てるわけではないことも知るのです。
私は、「思い通りにならないこと」がスポーツの価値を高めているのだと思っています。思い通りにならないとき、それを受け入れられずに閉じてしまっては、その先には進めません。
今大会で、真剣勝負の「偶有性」の中に身を置ける皆さんは、大変貴重な機会を得たと言えるでしょう。
勝っても負けてもそれを正面から受け止め、課題を探して次に活かすことが、競技レベルを上げると共に、皆さんの将来に向けた財産となるはずです。
さて、いよいよ勝負の時です。選手の皆さんは、一心にプレーするその姿で、皆さんに関わる全ての方に、勇気と感動を届けていただきたいと思います。
また、応援する生徒の皆さんは、自校の仲間に惜しみない声援を送り、選手とともに感動を分け合ってほしいと思います。
結びに、本大会の開催に当たり御尽力賜りました役員の皆様をはじめ、御指導いただいている関係者の皆様に深く感謝申し上げ、激励のことばといたします。
高校生の皆さん、精一杯頑張ってください。
第1回 山梨県高等学校・特別支援学校校長会(令和7年4月10日)
山梨県内の高等学校・特別支援学校の校長が集まる「校長会」に荻野教育長が出席し、次のとおり挨拶を述べました。
1.生徒主体の学びの実現
不登校児童生徒の増加が全国的な課題となっているが、本県も例外ではない。
ICTが普及していつでもどこでも学習動画が視聴できる時代、不登校を減らして行くためには、「何故学校に行く必要があるのか」という子供たちの問いに対して、彼らが納得できる理由を、教員を含めた大人が自分の言葉で語れるようにしなければならない。
そのためには、教員自身が学び続け、時代の変化を敏感に感じながら変わり続け、学校自体も変わっていかなければならないと思う。従って、教員の研修の在り方も変えていく必要がある。
私はサッカー部の指導を長年やってきたが、2001年1月にサッカー指導者を集めて行われた、フットボールカンファレンスにおいて、ジダンやアンリ、トレゼゲなどを擁しワールドカップで優勝した、当時世界最強と言われたフランス代表の監督ロジェ・ルメールの講演の中で、とても印象に残った言葉がある。
それは、「学ぶことをやめたら、教えることをやめなければならない」、「指導者になるということは、永遠に見つからない答えを見つけに行く旅に出たことを意味する」
この言葉は、今でも多くのサッカー指導者に影響を与えている言葉であろう。
教育振興基本計画では、生徒主体の授業への教育観の転換を謳っているが、教員がこれまでのやり方に固執せず、積極的に自身を変えていけるよう、総合教育センターを中心に、教員の研修観の転換にも取り組んでいくつもりである。
先生方には、是非ともたくさんの本を読んでもらいたいと思っている。自分の専門性を高めるための読書も大切だが、ジャンルを問わず様々な本を読んで、見識を広めてほしい。それが生徒に語る言葉に力を与えるはずである。
2.学校の先生方を元気にしたい
昨年度の校長研修会での上智大学、奈良先生の講話の中で、「不登校の子供の切実な声として、学校には、やらなきゃいけないこととやっちゃいけないことしかない。つまり、子供たちの『やりたいこと』がない。そして、昨今の教員の成り手不足も、根っこは同じである。」とのお話に感銘を受けた。
教科の授業を子供たちの「やりたいこと」にするためには、学習指導要領に明示してある各教科の目的を踏まえ、教員が主体的に授業をデザインすることが大切だと思う。教科書はそのための活動を例示しているにすぎない。教科書を教えることが目的ではないはず。また、ICTの活用は奨励しているが、使うことそのものが目的ではない。
不登校の児童生徒を減らすためにも、教員のなり手不足解消のためにも、まずは教員が生き生きと働き、子供たちが通いたいと思い、教員に憧れてくれるような学校現場にしていくことが大切である。
教員が自ら学ぶためには、余白の時間が必要であり、そのための働き方改革だという趣旨を保護者や地域の方々に理解してもらい、力を合わせて先生方を学校外からも支えていただけるような気運を高めていきたい。
R8年度を目処に全県立学校で導入を予定しているコミュニティスクールは一つのきっかけになると思う。
よい教育のための必要条件は、教員が日々笑顔で元気よく、子供たちに相対することだと思っている。その意味でも、校長先生方にはまずはご自身の健康に留意されて、その上で、先生方の心身の健康に目を配ってほしい。
先生方一人一人が学校にとっては貴重な戦力である。気になる先生や課題を持っている先生に対しては、校長自ら積極的に声をかけ、話をすることをおすすめする。
会話の中で、その先生の長所を見つけて積極的に認めることで自己有用感を高め、彼らが自分の長所を発揮して少しでも学校に貢献できるよう、助けてあげてほしいと思う。
教員出身の教育長に何か利点があるとすれば、施策に現場の目線を活かすことができる点にあると思う。教諭や教頭・校長として先生方や子供たちと関わってきた経験を教育行政に反映させていきたい。
一方で、自分の経験は一部の高校現場に限られている。それを自覚して、まずは視野が狭くならないよう、できるだけ現場を見せていただきながら、私自身が学び続ける姿勢を持つことが大切だと思っている。
「子供たちの人格の完成を目指す」という教育の本質を見失わないように気をつけながら、山梨の教育が少しでもよくなるよう、邁進していきたい。
新教育長の就任記者会見(令和7年4月2日)
令和7年4月2日、新たに山梨県教育委員会教育長に就任した荻野智夫が就任記者会見を行い、次のとおり抱負を述べました。
昨年度1年間、教育監として降籏前教育長の下で学んだことを活かし、その成果を継承しながらさらに深化させていきたい。具体的な目標として3点を挙げたい。
1.少人数教育の推進
制度としての25人学級は、R7年度に5年生に、R8年度には6年生に導入することが決まっており、小学校全学年で少人数学級が実現する。昨年度の検討委員会で、少人数教育の効果は確認されているが、今後は少人数の利点を活かした、更なる教育の質の向上を図っていく。
課題となるのが、教員不足であることは承知している。選考検査の工夫や教員の魅力発信を根気よく進めていきたい。
教員の魅力向上のためには、教員の働き方改革を進めていく必要がある。昨年度末に、今後5年間の新しい働き方改革取組方針を定めたところであるが、今年度からの新しい取組として、全ての学校に指導主事を派遣してワークショップを実施し、教員が自らの働き方を見つめ直し、自分事として改革に取り組めるよう指導して参りたい。
また、教育委員会では、昨年度末に教員の魅力や教員への感謝の気持ちを伝える動画を作成し、公開した。今後も、豊かな自然や少人数教育など山梨県で教員として働くメリットを、県内外に広く伝える努力を継続したい。
教員は大変なこともあるが、とてもやりがいのある仕事である。私自身、毎年卒業式を迎える度に涙してきたが、毎年感動で泣ける仕事は、そんなにないのではないか。そんな教員の魅力を、個人的にもできるだけ伝えていきたい。
2.生徒主体の学びの実現
不登校児童生徒の増加が全国的な課題となっているが、本県も例外ではない。学校に通いにくくなってしまった児童生徒に学びの場を提供する「学びの多様化学校」や、十分な教育を受けられずに中学校を卒業した方々を対象とした「夜間中学」の設置に向けた検討を進めていく予定である。
ICTが普及していつでもどこでも学習動画が視聴できる時代、「何故学校に行く必要があるのか」という子供たちの問いに対して、彼らが納得できる理由を、教員を含めた大人が自分の言葉で語れるようにしなければならない。
そのためには、教員自身が学び続け、時代の変化を敏感に感じながら変わり続け、学校自体も変わっていかなければならないと思う。従って、教員の研修の在り方も変えていく必要がある。
教育振興基本計画では、生徒主体の授業への教育観の転換を謳っているが、教員がこれまでのやり方に固執せず、積極的に自身を変えていけるよう、総合教育センターを中心に、教員の研修観の転換にも取り組んでいくつもりである。
個人的には、先生方には、是非ともたくさんの本を読んでもらいたいと思っている。自分の専門性を高めるための読書も大切だが、ジャンルを問わず様々な本を読んで、見識を広めてほしい。それが生徒に語る言葉に力を与えるはず。
3.学校の先生方を元気にしたい
不登校の児童生徒を減らすためにも、教員のなり手不足解消のためにも、まずは教員が生き生きと働き、子供たちが通いたいと思い、教員に憧れてくれるような学校現場にしていくことが大切である。
働き方改革の趣旨を保護者や地域の方々に理解してもらい、力を合わせて先生方を学校外からも支えていただけるような気運を高めていきたい。R8年度を目処に全県立学校で導入を予定しているコミュニティスクールは一つのきっかけになると思う。
特に若い先生方を見守り育てる視点を、保護者や地域の皆様にも持っていただけるようにできたらと思っている。
教員が子どもと向き合う時間を生み出すための働き方改革だが、教員が精神的な健康を保つ意味でも、各自の時間の使い方に工夫が必要。
よい教育のための必要条件は、教員が日々笑顔で元気よく、子供たちに相対することだと思っている。その意味でも、仕事とプライベートを区別して、仕事以外に打ち込めるものや楽しみを持ち、私生活の部分でも豊かな人生にしてほしい。
教員出身の教育長に何か利点があるとすれば、施策に現場の目線を活かすことができる点にあると思う。教諭や教頭・校長として子供たちと関わってきた経験を教育行政に反映させていきたい。
一方で、私の経験は高校現場に限られ、義務教育や特別支援教育については決して明るくない。学校を取り巻く状況は日々変化しているし、教育行政についても前教育長ほどの経験値はない。
そのことを自覚して、まずは視野が狭くならないよう、できるだけ現場を見ながら、私自身が学び続ける姿勢を持つことが大切だと思っている。
「子供たちの人格の完成を目指す」という教育の本質を見失わないように気をつけながら、山梨の教育が少しでもよくなるよう、邁進していきたい。
 <荻野智夫・略歴>
<荻野智夫・略歴>
南アルプス市出身
学歴: S58.3巨摩高校卒。S62.3筑波大卒、専攻は数学。H15.3兵庫教育大学大学院修士課程修了
教諭:韮崎工業高校、富士河口湖高校、甲府南高校
行政職:現在の総務課教育企画室で高校入試や高校改革を担当。甲府一高探究科、青洲高校の立ち上げ等
管理職:日川高校教頭、甲府昭和高校・都留高校校長、昨年度は教育委員会事務局教育監
降籏教育長
手島前教育長
三井前教育長
斉木前教育長
